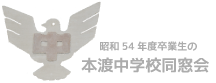たい焼きカフェまるきん / 熊本県天草
熊本県天草市中央新町の銀天商店街の一角にあるたい焼きカフェ「まるきん」です。「かんかんかん」と音を鳴らして焼くまるいかたちのたい焼きは、京都の老舗和菓子屋『俵…
中学生の頃に慣れ親しんだ「まるきん製菓」
現在、たい焼きカフェ「まるきん」として、高松聖司君が店主として頑張ってます。
天草を離れ、色々な土地で頑張ってる皆さん。
同窓会や帰省された折には、是非お立ち寄りください。

以下、「週刊現代」2024年1月13・20日合併号より
週刊現代
小山薫堂 (こやま・くんどう)さん/’64年生まれ。熊本県出身。放送作家。『料理の鉄人』など斬新なテレビ番組を企画。映画『おくりびと』で第81回米アカデミー賞外国語部門賞を獲得。下鴨茶寮主人、大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサー
「尾がない」たい焼きに劣等感
天草の実家から歩いて数分の距離に『まるきん』と呼んでいたお店があって、そこのたい焼きの形がまん丸だったんです。保育園のころからおやつといえばこれで、毎日のように食べていました。
ただ、このたい焼きは人生で初めて自分が「田舎者」であることを実感した物で、大ヒットした『およげ!たいやきくん』という歌に出てくるたい焼きには尻尾がついている。

小学生の僕は、丸いたい焼きしかない地元が世の中においていかれているような感覚を持ったんです。「頭から食べるか、尻尾から食べるか」というよくある論争がうらやましかった。
大学入学とともに上京して、当時四ツ谷にあった文化放送でアルバイトを始めたのですが、近くの老舗のたい焼きはもちろん尻尾つき。歌のモデルになった麻布十番の店にも行ってみると、主人が職人風情でさっそうと焼いていて、「これが本物のたい焼きなのか」と実感しました。
でも不思議なもので、大人になるにつれて、丸いほうがレアでカッコいいのではないかと思えてきたんです。実家に帰って食べてみるとたっぷりとあんこが詰まっていて、素朴でおいしい。心がほっこりする。
友に再建を託した
7、8年前でしたか、『まるきん』のご主人から「60年以上続けてきましたが、機械も故障したので閉店します」という手紙をもらったのです。ご主人に電話をして、壊れたのはたい焼き機ではなくてエアコンだと知り、「継ぐ人を探してもいいでしょうか」と思わず言っていました。
店の経営状態をきくと、一個90円という値段なので採算ぎりぎりか赤字。それなら地元の中高生に社会科見学のような形でやってもらってはと思い、保育園からの同級生で観光協会で働いていた高松聖司くんに相談したのです。
そうしたら「オレ、やるよ」と二つ返事でした。『まるきん』は僕ら2人の家の中間くらいにあり、彼にとっても大事な店だったのです。
高松くんは数日後に電話をしてきて、「観光協会は副業を禁止しているので辞めることにした」と言うので、「他を探すよ」と返事をすると、彼は「いや観光協会を辞めることにした」。
食っていけないよと反対したのですが、「もう辞めたから」と言われて。僕としては大変なことになったという思いでした。全国からファンがやってきて、通販でも売れるような商品にしなくては、と。
まず京都の『京菓子司 末富』という和菓子の名店のあんこがいいと聞いて、高松くんが若主人にあんこの炊き方を学びに行きました。また、神戸の『パティシエ エス コヤマ』のパティシエ小山進さんに監修をお願いして、生地作りだけでなく、あんこと天草の茶葉をまぜたクリームのハイブリッドのたい焼きにしよう、というアイデアを出してくれました。
ロゴなどのデザインはくまモンのクリエイティブディレクター水野学さんがほぼボランティアでやってくれて、それを『BEAMS』の設楽洋さんがTシャツなどのグッズにしてくれました。
「たい焼き」に込めた故郷への思い
高松くんは最初、観光協会を辞めて店をやることを奥さんに言い出せなくて、準備期間のある日、僕が訪ねたら「なんではじめから言わんとね」と奥さんにキレられてケンカになりそうだったので、僕も一緒になって謝りたおしました。でも、ご主人と僕が電話で話してほぼ1年後のオープンの日には、奥さんは誰よりも働いていましたね。
開店当初から県内のイベントに出店してほしいという依頼はあるし、普段から観光客も来てくれるのですが、一個150円ですから、そうは儲かりません。でも、観光客にたい焼きでひと息ついてもらっている間に天草観光の案内ができたらいいな、と。
高松くんはとてもいいやつで、観光客の中には彼のファンも増えているらしい。また福岡でラーメン店を開いた別の同級生が『まるきん』の味を福岡でもと言ってくれて、のれん分けの店も開く予定です。
僕は地方の人と食をテーマに「ふくあじ」というカテゴリーを作って、高級ではないけれど人々に愛される店を訪ね歩いているのですが、おいしさの本質って感情移入で、作ってくれた人への思いや作ってあげる人への思いそのものだと感じます。
おふくろの味も、愛妻弁当もそう。このたい焼きも子どものころのコンプレックスの象徴が自分の中で価値があるものになって、その価値観を幼なじみや同級生、そして多くの人々が共有してくれた。僕にとってはこそばゆくも誇らしい故郷そのものなのかもしれません。
取材・文/伊東武彦